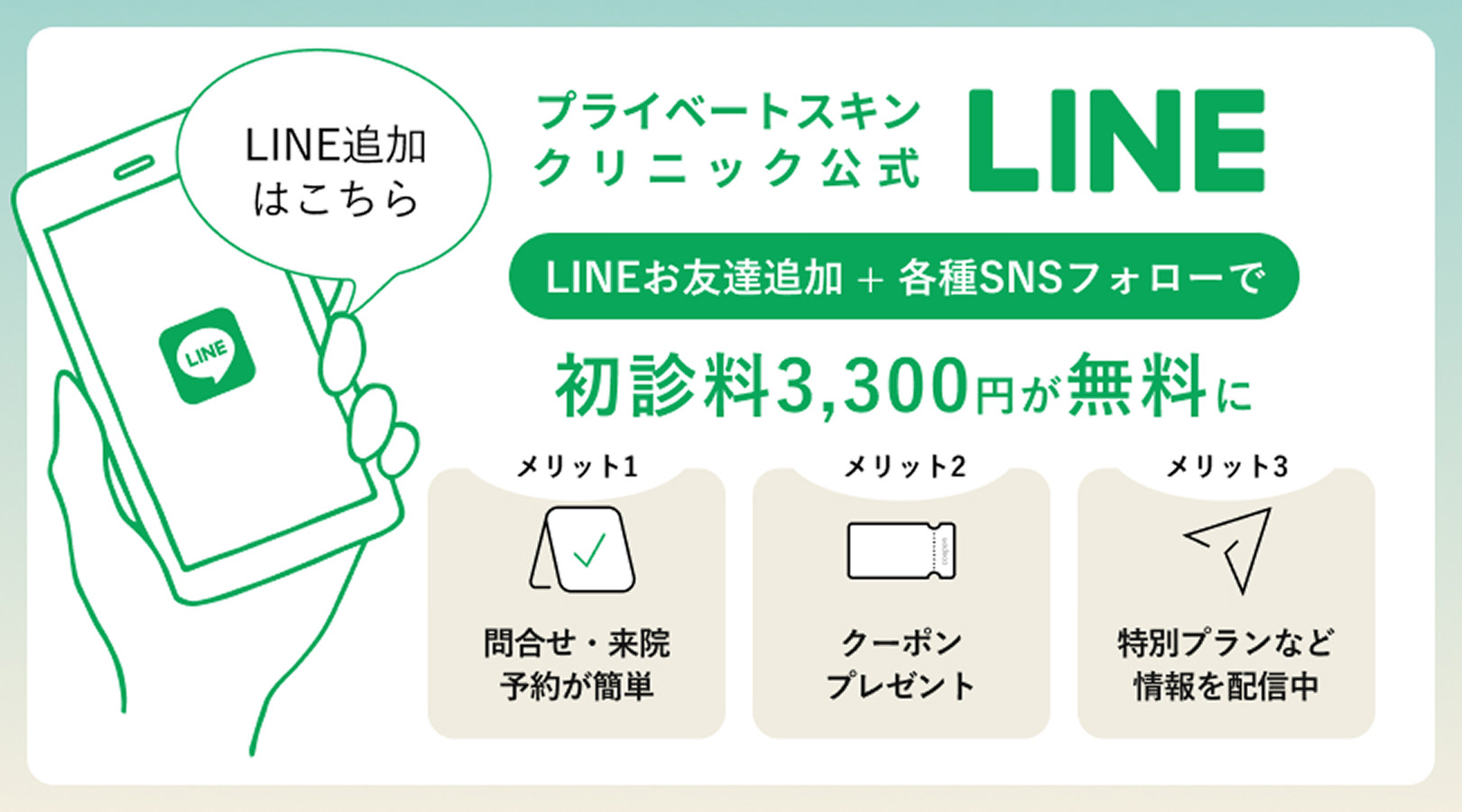耳介軟骨移植のダウンタイムとは?
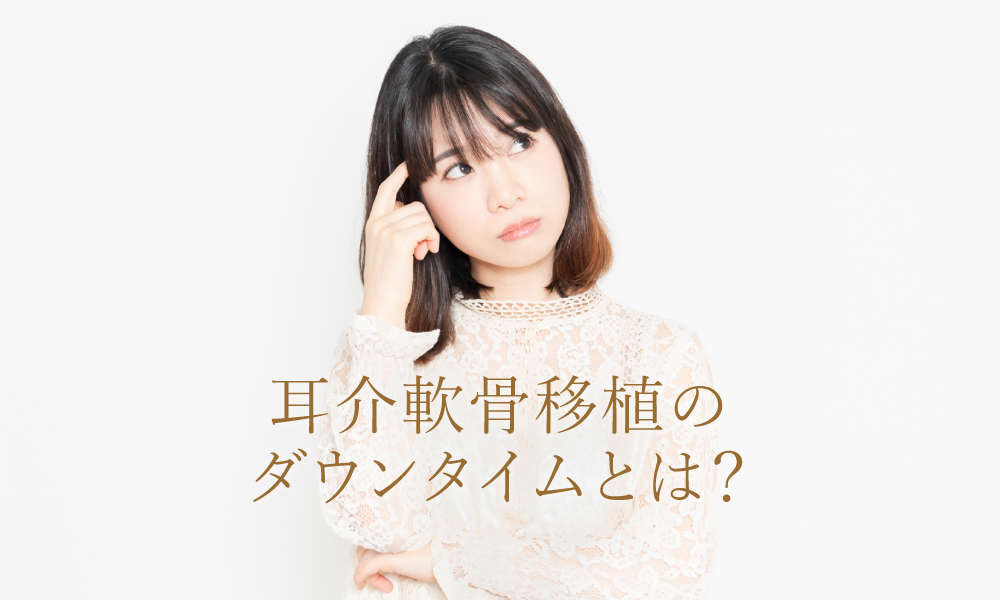
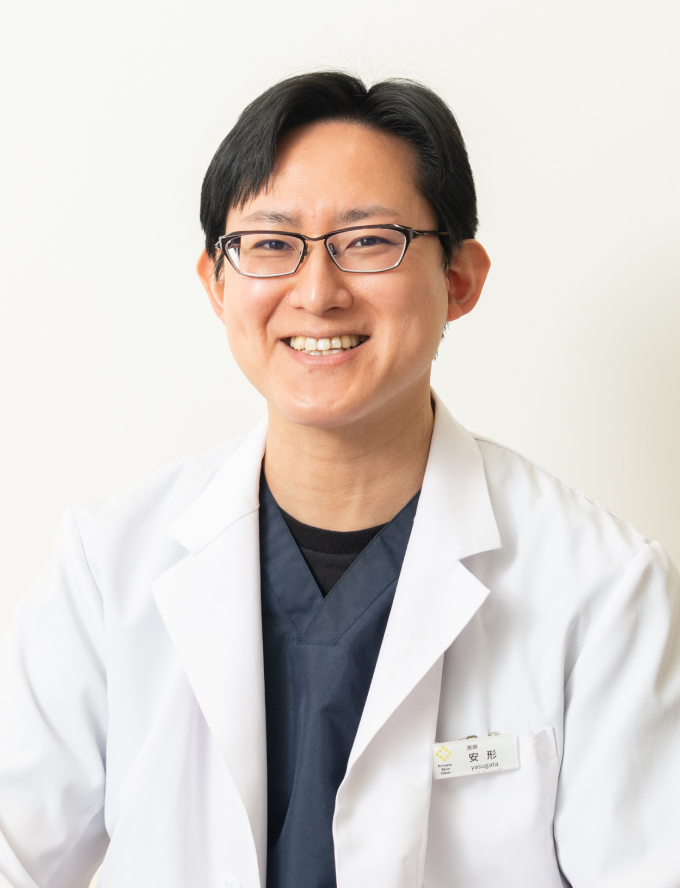
こんにちは!大阪梅田の美容外科・美容皮膚科のプライベートスキンクリニック院長の安形です!今回は、耳介軟骨移植のダウンタイムについてのご紹介です。
鼻先を高くしたり、豚鼻や団子鼻の治療に効果的な「耳介軟骨移植」。耳の軟骨を採取し鼻先に挿入する方法で、たった30分程度の短時間で完了する施術です。ご自身の軟骨を使用するため、アレルギー反応が起きにくいというメリットがありますが、耳と鼻の2箇所を切開する施術となれば、やはり気になるのはダウンタイムですよね。
そこで、本日は耳介軟骨移植のダウンタイムについて詳しく解説します。鼻整形で耳介軟骨移植をご検討中の方は、施術前に必ずチェックしてくださいね!
目次
耳介軟骨移植のダウンタイムはどのくらい?
耳介軟骨移植のダウンタイムは、個人差はありますが、1~2週間が目安となります。
耳の軟骨を切り取って鼻先に移植しますので、「耳」と「鼻」の両方にダウンタイムが発生します。また、団子鼻の改善手術として「鼻尖形成術(鼻尖縮小術)」を同時に受けた際も、ダウンタイムの目安は1~2週間程度です。
ダウンタイム中の鼻の症状と経過

鼻の症状としては、赤み、腫れ、内出血が生じる可能性があります。
腫れのピークは1週間で、腫れの症状が治まるまでに1~2週間程度かかります。
また、軽度の腫れ・むくみは2~3カ月程度続く場合があります。
内出血が生じた場合は、1~2週間以内に回復します。
傷口が治る過程で、痒みが生じることがあります。
術後1か月程度は、鼻先が硬く感じるケースがありますが、徐々に柔らかく変化していきます。
なお、極稀に合併症として、傷口から感染を引き起こす可能性があります。
移植した軟骨内部で感染が起こっている場合は、取り出す必要があります。
赤みや痛み、何かしらの違和感が2週間以上続く場合は、早急に施術を受けたクリニックにご相談ください。
【鼻の傷跡】
鼻の穴の内側から切開して軟骨を移植しますので、見える位置に傷跡はできません。
【施術後の状態と通院】
施術後は鼻先に入れた軟骨を固定するため、鼻先を覆うようにテープを貼ります。
1週間後に抜糸をし、その後は更に1週間夜のみテープ固定を行います。
ダウンタイム中の耳の症状と経過
耳の腫れや内出血が生じる可能性がありますが、1~2週間で治まります。
個人差はありますが、鼻とは異なり、耳は軽度の腫れですむ方がほとんどです。
施術後は、耳の痛みを感じたり、傷口が治る過程で痒みが生じるケースもあります。
【耳の傷跡】
耳介(じかい)、または耳珠(じじゅ)から軟骨を取り出しますが、基本的に目立たない位置を切開します。赤い線状の傷跡は徐々に回復していきます。
【施術後の状態と通院】
数日間、または抜糸までの間は、ガーゼやテープにて固定と保護を行います。
1週間後に抜糸を行います。
鼻尖形成術(鼻尖縮小術)併用時のダウンタイムの症状と経過
耳介軟骨移植は、よりシャープな鼻先を作ることができる鼻尖形成術との併用が可能です。
併用時の鼻の症状としては、赤み、腫れ、内出血が生じる可能性があります。
強い腫れは1~2週間以内に治まります。
腫れのピークは耳介軟骨移植単体の時と同様に、1週間程度です。
【鼻の傷跡】
鼻尖形成術は、術式によって切開位置が異なります。オープン法の場合、鼻柱に傷跡ができます。クローズ法の場合は、鼻の穴の中を切開しますので傷跡は目立ちにくくなります。
それぞれの術式でメリット・デメリットがありますので、施術前に確認が必要です。
【施術後の状態と通院】
施術後は、鼻先が動かないようテープ固定とギプス固定を行います。
術後、1週間程度でギプスを外します。
耳介軟骨移植施術後の過ごし方と注意点

耳介軟骨移植で特に注意が必要なのは、鼻への圧迫です。術後はテーピングにて固定しますが、鼻に力がかからないように、注意して過ごす必要があります。
また、激しい運動などの体を温める行動は、しばらく控えるようにしましょう。
行動制限の目安はクリニックによって多少異なります。必ずカウンセリング時に確認しておきましょう。
【術後】
シャワー、シャンプー、洗顔、メイクは当日より可能です。
患部を避けて行ってください。
【術後1週間まで】
うつぶせ寝はNGです。頭を高くし、「仰向け」または「横向き」で寝るようにしましょう。
腫れやかゆみがあるときは、冷やすのがおすすめです。
【術後1か月まで】
鼻のマッサージ、鼻を強く抑える、鼻を強くかむなど、鼻に負担がかかる行動は控えてください。
耳介軟骨移植は周囲にバレる?バレない?
耳介軟骨移植でバレやすい部分は、施術後の固定や保護で使用するテープ・ガーゼの存在と鼻の腫れです。
術後は、鼻の軟骨を固定するためのテープを貼りますので、どうしても目立ってしまいます。腫れは、2週間程度はわかりやすい状態となる可能性があります。
バレないように過ごすには、マスクを活用するのがおすすめです。
また、耳に装着するガーゼは、長い髪の方であれば隠れますし、「ピアスで化膿した」「マスクで炎症を起こしてしまった」などの理由でごまかす方法もあると思います。
絶対バレたくないのであれば、テープやガーゼが取れて、腫れがひくまでの間、人と会うのを制限するのが無難と言えるでしょう。
まとめ
耳介軟骨移植のダウンタイムについてご紹介しました。耳と鼻の両方で、それぞれに症状があることがおわかりになったと思います。
ヒアルロン酸注射などのプチ整形に比べると、どうしてもダウンタイムは長くなりますが、シャープな鼻先を半永久的にキープできる施術となりますので、メリット、デメリットを比較してご検討いただければと思います。
大阪梅田のプライベートスキンクリニック(PSC)では、患者様一人ひとりにぴったり合った施術プランをご提案いたします。
耳介軟骨移植をご検討中の方、鼻整形にご興味のある方は、当クリニックへお気軽にご相談ください。
医師・スタッフ一同心より皆様のご来院をお待ちしております!
よくあるご質問
患者様からよくいただく質問をご紹介します。
耳介軟骨移植のダウンタイムはどのくらいですか?
耳介軟骨移植のダウンタイムは、1~2週間程度です。耳と鼻の両方に症状があります。
鼻の腫れのピークは1週間です。腫れが引くまでは、マスクをつけて過ごしましょう。
耳介軟骨を採取した後は、耳はどうなりますか?
耳の軟骨の一部を採取しますが、耳の形に影響はありません。
軟骨を切除した部分は、以前より柔らかい手触りとなりますが、時間が経つと軟骨膜内で軟骨が多少は再生されますので、徐々に改善されます。
耳介軟骨の採取によって、イヤホンが装着できなくなることがありますか?
基本的にイヤホンが着けられなくなることはありません。ただし、軟骨を取り出す位置や軟骨の大きさによっては、イヤホンやマスクが安定しにくくなるケースがあるようですので、影響についてはカウンセリング時に必ず確認しましょう。
鼻に入れた軟骨がずれることはありますか?
術後、一定期間を過ぎれば、ずれることはありません。周りの組織と馴染むまでの間は、鼻に負担がかからないように注意が必要です。
耳介軟骨移植の抜糸はいつ行いますか?
抜糸は、術後1週間程度で行います。
抜糸の後、徐々に腫れが目立たなくなり回復していきます。
耳介軟骨移植で合併症は起こりませんか?
確率としてはとても低いのですが、極稀に施術の際の傷口から感染を引き起こすケースがあります。赤みや痛み、違和感が続くという場合は、早急に施術を受けたクリニックにご相談ください。
耳軟骨移植のデメリットはありますか?
耳介軟骨移植のデメリットは、切開による鼻整形ですので、ダウンタイムがあり、術後、1週間程ギプスやテープで鼻先が動かないように固定します。2週間程は腫れが分かりやすい状態なので、マスクで隠したり人に会うスケジュールを調節される方もいらっしゃいます。
| 美容外科・ 美容皮膚科 |
西梅田駅から徒歩2分 プライベートスキンクリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル2階 |
| 診察時間 | [ 完全予約制 ] 10:30~19:00 |
DOCTOR.
このページの監修医師
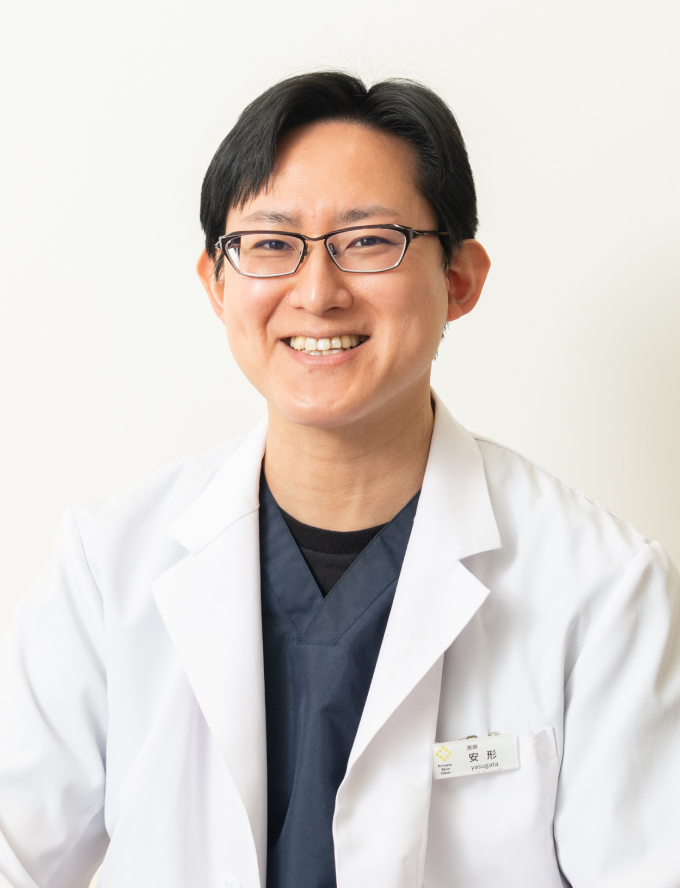
資格
- 一般社団法人日本形成外科学会 形成外科専門医
- 一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会 正会員
- 一般社団法人日本創傷外科学会 正会員
- アラガン社 VST(ボトックスビスタ)認定医
- アラガン社 ヒアルロン酸バイクロスシリーズ注入認定医
- Miramar Labs社(ミラドライ開発社)ミラドライ認定医
経歴
| 平成14年 | 大阪医科大学医学部医学科:入学 |
|---|---|
| 平成22年 | 大阪医科大学付属病院 形成外科学教室:入局 |
| 平成23年 | 守口敬任会病院:入職 |
| 平成25年 | 東住吉森本病院:入職 |
| 平成27年 | 大阪医科大学付属病院 形成外科学教室:入職 |
| 平成28年 | 東住吉森本病院:入職 |
| 平成30年 | プライベートスキンクリニック:入職 |
学会発表
- 第67回 日本形成外科学会総会・学術集会(2024年4月10日~12日)
- ヒアルロン酸によるたるみ・ほうれい線改善治療における100症例の経験及び考察
- ヒアルロン酸による鼻の整形93症例の経験及び考察