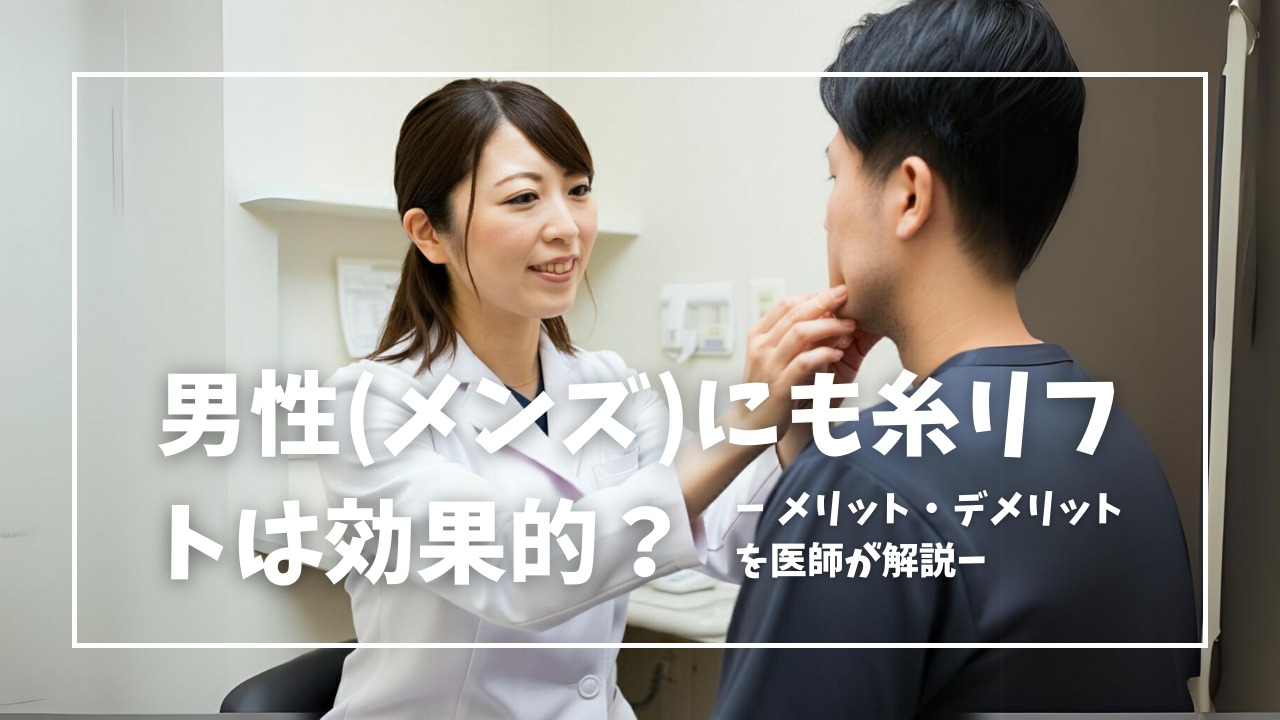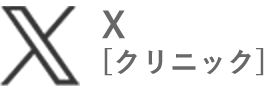男性にも医療ハイフ(HIFU)がおすすめの理由

肌のたるみやハリ不足、さらにテカリや毛穴の開きなど肌トラブルに悩む男性も少なくありません。
そんなお悩みにアプローチできるのが「ハイフ(HIFU)」です。
切らずに手軽にリフトアップが目指せる美容医療として、近年は男性からも注目を集めています。
そこで本記事では、男性がハイフを受けることで得られる効果やメリット、そして知っておきたいデメリットや注意点についても詳しくご紹介します。
もくじ
そもそもハイフ(HIFU)とは?
ハイフは「高密度焦点式超音波」と呼ばれる特殊な超音波を使った美容施術です。
皮膚の表皮層から皮下脂肪、さらにその奥にある筋膜(SMAS層)まで熱エネルギーを届けることで、肌の引き締めやリフトアップ効果が期待できます。
さらに、肌の弾力やうるおいを支えるコラーゲンやエラスチンの生成も促され、ハリやツヤのある肌へと導きます。
ハイフは皮膚の表面を傷つけることなく、深い層にまで働きかけられるのが特長です。
美容医療の中でも比較的受けやすい施術なため、男性にも気軽に受けていただけます。
今回はハイフの効果に加えて、メリット・デメリットを詳しく解説いたします。

男性のハイフはどんな効果がある?
肌の深い層までアプローチできるハイフには、どんな効果があるのか気になりますよね。
ハイフは引き締めやリフトアップだけでなく、テカリや毛穴などの肌質改善にも効果が期待できます。
ここからは、男性がハイフで得られる効果を4つに分けてご紹介します。
小顔・引き締め効果
小顔になりたい、フェイスラインを引き締めたいと考える男性も少なくありません。
ハイフは皮膚の奥にある皮下組織やSMAS層に熱エネルギーを与えることで、顔全体の引き締めや小顔効果が期待できます[1]。
肌の引き締めやリフトアップは、スキンケアやマッサージだけでは変化を感じにくいことが多いです。
ハイフは肌のセルフケアでは届かない肌の深層までアプローチできるため、一時的な変化ではなく持続的な効果を実感できます。
顔のテカリなど肌質を改善
ハイフは顔のテカリや肌質を改善したい男性にも効果的な施術です。
皮膚の奥にある真皮層に超音波を当てると、コラーゲンやエラスチンが活性化します。
コラーゲンは、角質の水分量を高めて肌のハリを保つ働きを担っていますが、年齢とともに減少していくのが特徴です。
ハイフによってコラーゲンの生成が促されることで、ハリや弾力の向上、保湿力アップなどの効果が期待できます。
特に、男性の肌は皮脂量が多いため、肌の水分バランスが整うと過剰な皮脂分泌も改善されるでしょう。
たるみ・ほうれい線を軽減
男性も年齢を重ねると、顔のたるみやほうれい線が気になってくる方が多いのではないでしょうか。
この原因のひとつに、皮膚の土台となる「SMAS層(スマス層)」の衰えがあります。
ハイフは熱エネルギーでSMAS層を引き上げ、たるみを根本からケアできる点が特徴です。
さらに、コラーゲンやエラスチンの生成が活性化されることで、ほうれい線や小ジワの改善も期待できます。
たるみ治療には糸リフトなどの美容医療もありますが、より手軽に受けたい方や、異物を入れるのに抵抗がある方はハイフの方が適しています。
脂肪へのアプローチ
ハイフは脂肪にもアプローチできるため、顎や頬の脂肪が気になる男性にもおすすめです。
特に顔の脂肪は落としにくく、ダイエットでは変化を感じにくい部分でもあります。
気になる箇所にピンポイントで照射できるのもハイフの特長で、複数回受けるとより効果を実感しやすくなります。
また、極端な体重の増加がなければ効果が長持ちしやすく、元の状態に戻りにくい点も魅力です。
脂肪吸引のようなメスを使う施術に抵抗がある方にも気軽に受けていただけます。
ハイフのメリットとは?
美容医療には、ハイフ以外にも肌の引き締めやリフトアップに効果が期待できる施術があります。
その中でも、なぜハイフが選ばれているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ハイフの主なメリットを4つに分けてご紹介します。

痛みを感じにくい
ハイフは施術時の痛みが少なく、麻酔なしでも受けられるのがメリットです。
部位によってはピリピリとした刺激を感じることもありますが、ほとんどの方が我慢できる程度とされています。
また、メスを使わない施術のため、肌表面のダメージを抑えたい方にもおすすめです。
切開や注射に抵抗がある方でも試しやすく、美容医療が初めての男性にも取り入れやすいでしょう。
ダウンタイムが少ない
ハイフはダウンタイムが少なく、施術後に強い腫れや痛みが出ることはほとんどありません。
施術後は軽い赤みや火照りが生じる程度で、すぐに日常生活に戻れるのもメリットです。
一方、メスを使う施術はダウンタイムが長引く傾向があり、傷跡が残るなどリスクを伴います。
ハイフは皮膚表面へのダメージが少ないため、施術を受けたことも周りに気付かれにくいでしょう。
仕事やプライベートで忙しい男性も、ぜひ検討してみてください。
効果を実感しやすい
ハイフは効果を早く実感しやすく、施術直後に変化を感じる方もいます。
遅くても1ヶ月以内には効果が現れるため、できるだけ早く結果を得たい方にもおすすめです。
ハイフの効果は術後1〜2ヶ月をピークに徐々に落ち着き、半年ほどで薄れていくとされています。
そのため、理想の状態を保ちたい場合は、定期的に施術を受けると効果を持続しやすくなるでしょう。
なお、感じ方や持続期間には個人差があるため、あくまで目安としてお考えください。
施術時間が短い
ハイフの施術時間は短く、ショット数にもよりますが40分以内で終了することが多いです。
ショット数にもよりますが40分以内で終わるケースもあり、忙しい男性でも手軽に受けていただけます。
美容医療の施術は長引くことも多く、日常生活への影響を気にされる方も少なくありません。
一方、ハイフは短時間で効果を実感しやすく、美容医療の中でもハードルが低い施術です。
家事や仕事のスキマ時間にも通えるため、男女問わず人気を集めています。
ハイフのデメリットや注意点は?
ハイフには多くのメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットやリスクもあります。
特に、施術後の副作用やアフターケアについては、事前に確認しておくと安心です。
そこで今回は、デメリットや注意点を4つのポイントにまとめました。
糸リフトに比べると効果を感じにくい
糸リフトは、医療用の極細な糸を用いて物理的にたるみを引き上げる施術です。
ハイフにも引き締めやリフトアップの効果が期待できますが、たるみがとても強い場合は変化を感じにくい場合もあります。
ただし、どの施術が合っているかは人によって異なるため、医師と相談しながら決めることが大切です。
当クリニックでは、お一人おひとりの状態に合わせて、医師が最適な施術をご提案いたします。
気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
施術後は肌が乾燥しやすい
ハイフの施術後は、一時的に肌が敏感になり、刺激を受けやすい状態になります。
乾燥したまま放っておくと、肌トラブルの原因になることもあるので注意が必要です。
外出時は紫外線対策をしっかり行い、保湿を中心としたスキンケアを心がけましょう。
なかでも、セラミドやアルヒロン酸など保湿力の高い成分を含んだクリームがおすすめです。
また、洗顔後はタオルでこすらず、やさしく包み込むように水分を拭き取ってください。
腫れや痛みが出ることもある
ハイフは術後の副作用が起こりにくい施術ですが、赤みや腫れ、浮腫みなどが生じることが非常に稀にあります。
これらは熱によるダメージが原因で、通常は数日〜数週間ほどで自然に治まります。
症状を悪化させないためにも、保湿をしっかり行い、摩擦や刺激を避けるようにしましょう。
また、施術後は激しい運動や長時間の入浴は控え、安静に過ごすことも大切です。
数日経っても赤みや腫れ、痛みが強く続く場合は、我慢せず医師に相談してください。
照射しすぎると頬が痩ける
ハイフは肌を引き締めたり脂肪にアプローチできる一方で、照射しすぎると頬がこけてしまうリスクがあります。
特に、顔の脂肪が少ない方や痩せ型の方は、頬のボリュームが減ると老けた印象になりやすいので注意が必要です。
一度照射した部位は元に戻すことが難しいため、あらかじめ医師と照射部位についてしっかり相談しておきましょう。
また、ハイフは継続すると効果を実感しやすい施術ですが、やりすぎを避け、必要な回数や範囲内で留めることも大切です。

医療ハイフとエステハイフの違いは?
ハイフは医療行為にあたるため、本来は医療機関でのみ施術が認められています。
それにもかかわらず、医療資格を持たないエステサロンでハイフを行うケースが問題視されてきました。
エステハイフは手軽で安価に受けやすい一方で、医師や看護師などの医療従事者がいないため、トラブルが発生するリスクが高いといえます[2]。
そもそも皮下組織に熱を加えるハイフは医療行為に当たるため、安全に行うには医療従事者による専門的な判断と技術が欠かせません。
ここでは、「医療ハイフ」と「エステハイフ」の違いについて詳しく解説します。
出力と効果の違い
医療ハイフは、60〜70℃の温度で照射する高出力の医療機器をします。
肌の奥深くにアプローチでき、根本的なリフトアップや引き締め効果が期待できるのが特徴です。
一方、エステハイフは、低出力の機器を使用するので医療ハイフのような効果は見込めません。
また、医療資格のないスタッフが行うため、火傷や神経損傷などの健康被害のリスクが高まります。
持続性と施術頻度の違い
医療ハイフは、通常1回の施術で3〜6ヶ月ほど効果が持続するとされています。
次回の施術はおおよそ3ヶ月後から受けられるため、3〜6ヶ月に1回のペースで続けるのが効果的です。
一方、エステハイフの持続期間は1〜2ヶ月程度とされています。
医療ハイフよりも効果が期待できず、通う頻度も多いので割高になるケースも多いです。
価格帯の違い
医療ハイフの価格はクリニックによって異なりますが、1回あたり2〜4万円程度が目安とされています。
エステハイフは医療ハイフより料金が安く見えるものの、施術回数が増えることで結果的に費用がかさむ傾向があります。
総合的にみても医療ハイフを受けた方がよいでしょう。
男性の医療ハイフはPSCforMENへ!
今回は、男性に向けたハイフの効果やメリット・デメリットについてご紹介しました。
ハイフは肌の引き締めやリフトアップ、肌質の改善などさまざまな効果が期待できます。
また、施術時間が短く、ダウンタイムもほぼないので忙しい男性にもおすすめです。
当クリニックでは、形成外科医出身の経験豊富な医師が患者様一人ひとりに合わせたプランをご提案いたします。
医療ハイフを検討している男性は、ぜひお気軽にご相談ください。
#男性 #医療ハイフ #たるみ #小顔
男性のハイフについてよくある質問
Q.ハイフをやめた方が良い人はいますか?
A.ハイフはお顔の脂肪を少ない方は、頬のコケが目立つようになるので注意が必要です。
また、たるみが強いとハイフの効果が実感できないケースもあります。
不安な点があれば、ぜひカウンセリングでご相談ください。
Q.糸リフトとハイフは併用できますか?
A.糸リフトで使用される「金の糸」は、ハイフの熱に反応して火傷を引き起こす可能性があります。
ただし、金の糸以外の素材であればハイフの施術も可能なため、併用される方もいらっしゃいます。
事前に医師へご相談いただくのがおすすめです。
Q.ハイフは発がん性がありますか?
A.HIFU(ハイフ)の施術が直接的に発がん性を引き起こすという報告はありません。
ハイフは超音波によって皮膚の深部に熱エネルギーを加える技術であり、美容医療の現場でもその安全性は確認されています。
参考文献
[1]U.S. Food and Drug Administration「Assessing the safety and effectiveness of new and emerging therapeutic ultrasound technologies」
https://www.fda.gov/science-research/about-science-research-fda/assessing-safety-and-effectiveness-new-and-emerging-therapeutic-ultrasound-technologies
[2]消費者庁「−エステサロン等での HIFU(ハイフ)による事故−」
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_01.pdf
関連記事
所在地 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-16 京富ビル2階
TEL 06-6940-7101
FAX 06-6940-7102
受付時間 10:30〜19:00 (完全予約制)
この施術ページの監修医師
医療法人優聖会最高顧問井畑 峰紀
糸リフトやフィラー注入によるしわ・たるみ治療や、にきび治療などの美肌治療を中心とした美容医療に携わる、確かな実績を持つ医師。

糸リフトやフィラー注入によるしわ・たるみ治療や、にきび治療などの美肌治療を中心とした美容医療に携わる、確かな実績を持つ医師。
所属
- 平成15年
- 大阪医科大学 形成外科教室:入局
- 平成21年
- 大阪医科大学 助教(准):就任
美容クリニック非常勤勤務:歴任
- 平成24年
- 医学博士学位取得
日本形成外科学会 専門医認定
- 平成25年
- 某美容クリニック:院長就任
- 令和5年
- プライベートスキンクリニック
最高顧問:就任 現在に至る
略歴
- 一般社団法人日本形成外科学会 形成外科専門医
- 特定非営利活動法人日本レーザー医学会 認定医
- 一般社団法人国際抗老化再生医療学会 正会員
- 一般社団法人 日本美容外科学会 JSAPS(Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery) 正会員
- 一般社団法人日本美容皮膚科学会(Japanese Society of Aesthetic Dermatology 正会員
- 一般社団法人日本頭蓋顎顔面外科学会 正会員
- アラガン社 VST(ボトックスビスタ)認定医
- アラガン社 ヒアルロン酸バイクロスシリーズ注入認定医
- Miramar Labs社(ミラドライ開発社)ミラドライ認定医